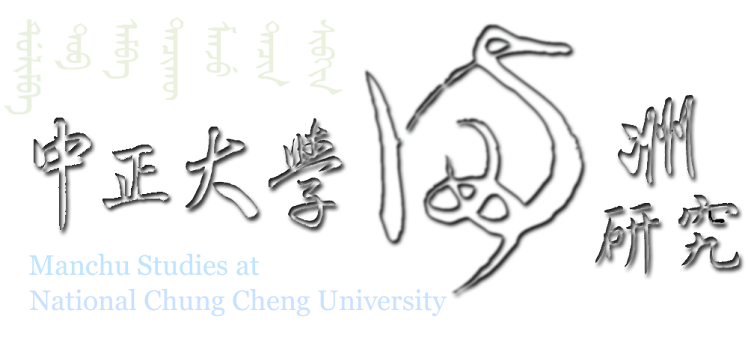常設国際アルタイ学会(PIAC)の45年:
歴史と回想(1)
デニス・サイナー著 宮脇 淳子訳
『第40回国際アルタイ学会議事録』(2)で、私はこの組織の歴史を概観した。私はそのときこう述べた。「こういうことをするのは50回目の議事録の方がもっとふさわしいが、それは難しい。その時には私はこの世にいないだろうし、私だけがすべての会議に出席し、私ほどPIACの継続に深く関わった者は他に誰もいないから」と。あれから5年過ぎたが、PIACはなお繁栄しているし、私もまだ生きているので、この片々たるニュースレターに、もう一度歴史を更新して掲載するのも悪くないかもしれないと考えた。実際、PIACニュースレターの方が、第40回会議録よりも読者が多いだろう。
PIACを創ったのは、偉大なモンゴル学者ワルター・ハイシヒ教授(ボン大学中央アジア研究所の創設者)である。ミュンヘンで開かれた第24回国際東方学者会議(ICO)の最中、彼はアルタイ部会の参加者に呼びかけて、「ICOのような大きな会議は、あまり有名でないアルタイ学を専門とする、少数の学者たちが意見交換する場としてはふさわしくない」という自分の考えを披露した。今でも同じだが、当時、たとえば、聖書研究、イスラム研究、中国学などに較べて、アルタイ学者の数は本当に少なかった。今から思うと、純粋なモンゴル学者であるハイシヒが、自分の研究分野は、トルコ系やツングース系を含む、より大きな単位と有機的関連があると感じていた、ということが私にとって興味深い。
1957年9月4日、われわれ10名ほどがミュンヘン大学の汚い部屋に集まって、ハイシヒの提言を聞いた。ハイシヒと私の他に誰がいたかは、アンネマリー・フォン・ガバインとオメリヤン・プリツァク以外は思い出せない。その時私は、新しい東方学者の組織が必要とは思わず、提案者への友情からこれを支持しただけで、何も起こらないだろうと確信していた。私が間違っていたことはすぐに明らかになった。ハイシヒは自分自身で最初の会議を組織したのである。
1958年6月25日から28日、マインツの科学文学アカデミーで第1回会議が開かれた。出席したのは、ペンティ・アアルト、チャールズ・ボーデン、ゲルハルト・デルファー、ヴォルフラム・エバーハルト、ワルター・ハイシヒ、カール・ヤーン、カール・メンゲス、ウド・ポッシュ、オメリヤン・プリツァク、クラウス・ザガスター、デニス・サイナー、カーレ・トムセン・ハンセンである。わずか12名であるが、6ヵ国からの参加で、幸先のよい始まりだった。社会主義諸国の学者も招いた。何人かは祝意を送ってきたが、誰も参加できなかった。
われわれはテーブルを囲んだ。「諸言語関係の性質の一般論」というアアルトの発表のような正式な論文も若干あったが、大部分の議論は、今後の研究の進展と、これを可能にするアルタイ学の必要性に集中した。参加者は、自分自身の仕事だけでなく、彼らの所属する大学や、さらにはソ連(プリツァク)や米国(メンゲス)など国家全体の学界事情について報告した。これが、のちのすべてのPIAC会議の特徴となる「コンフェッションズ(告白)」の手本となった。この時企てられた計画のいくつかは実行され、ここで提案された考えの中で、何年もたってから実現したものもある。
PIACが正式に創立されたのは1957年の会議で、この時、常設国際アルタイ学会Permanent International Altaistic Conference という名前が採用され、ワルター・ハイシヒが書記長Secretary Generalに選ばれた。私の知る限り、PIACはドイツで学会として登録されたことはなく、米国で登録されたこともない。
PIACが生き残り繁栄したのは、幸先のいいスタートのせいである。組織力にかけては天才のヘルムート・シェールが支持してくれ、彼が創ったマインツの科学文学アカデミーは、創設されたばかりのPIACを助けてくれた。アカデミーは、われわれの初め2回の会議の場所を提供してくれたが、これがのちの会議開催の手本となった。その場で討論するだけでなく、われわれ全員がそこに泊まり、食事を共にした。それは研究者の会合というよりも、のちにそう呼ばれるようになった「PIAC家族」である友だちの集会だった。
1959年6月23~28日の第2回会議では、参加者は12名から23名に増えた。エバーハルトを除いて第1回の参加者全員が参加し、強力な代表団がトルコ(マンスルオウル、オゲル、ラフメティ・アラト、アフメト・テミル)とイタリア(ボンバチ、ガンジェイ)から加わった。唯一の社会主義国の代表として、ザヤンチコウスキが初めてPIACに参加した。
マインツのアカデミーの建物が修理中だったので、1960年6月26日から7月1日の第3回会議は、ライン河の岸辺に高くそびえる、カンプ・ボルンホーフェンを望むリーベンシュタイン城の景色のよい場所で開催された。19名の参加者の中には、ニコラス・ポッペ、ワルター・フックス、エーリヒ・ヘーニシュといった長老たちが、学生とともに含まれていた。われわれの会が、若い世代に開放され拡大していくのは大歓迎だった。若い学者たちを招くという慣例はその後ずっと続いている。
リーベンシュタイン城の会議で特筆すべきことは、地元産ワインを味わう豊かな機会を提供してくれた、気取らないゲステハウス(宿屋)である。PIAC参加者たちが、ラインラントのぶどう農家の生産品のまことによき利用者で、その結果、学問的討論の最終日には、愉快で高揚した会話や歌が残されたことは、書き記しておくべきだろう。
カール・ヤーンは無尽蔵のジョークを蓄えており、しかも天才的な語り手だった。第2回会議のある夜、われわれ全員がワインケラー(酒場)へ席を移した。宿へ戻るのに、皆がフォルクスワーゲン製バスの中に押し込められ、リチャード・フライが少しでも窮屈でなくなるよう足の置き場を変えようと努力していた時、ヤーンが再びジョークを話し出した。ジョークが面白いだけでなく、彼は話すこつを知っていた。彼のウィーン風アクセントは、悲しい話をおかしくするのに十分な効果があった。すぐにわれわれはげらげら笑い転げ、突然フォルクスワーゲンが急停止して、ようやく浮かれ騒ぎが止んだ。車は堅いレンガ壁にあと2、3メートルの所で止まっていた。運転手が笑い転げて道に迷い、暗闇の中、袋小路に入ったのだった。もうちょっとで地元の病院は、治療の必要なアルタイ学者であふれていたところだった。
初め3回の会議は、連邦内務省の文化講演部から補助金を受けた。参加者が宿泊費を払ったかどうか、私は思い出せない。第3回会議の際には、ハイシヒが学生たちと二人のポーランド人の経費を肩代わりしたと思う。3回続けて補助金を受けたので、助成をしてくれる別の財源を探す必要があるという厄介な任務が生じた。そういうことだったのかどうか、ハイシヒは自分は十分にやったから、別の誰かがPIACを運営する時期だと感じた。それで彼は職を辞し、私が書記長に選ばれた。私は当時ケンブリッジ大学東洋学部で教えており、次のPIAC会議をイギリスのケンブリッジで開こうとしていたからである。
私はためらうことなく任務を引き受けた。ケンブリッジ大学は、どんな会議、シンポジウム、セミナーにも理想的な場所だったし、私はいくつかのカレッジと関係を持っていた。私は、当時はまだカレッジではなく、ローマ・カトリック教の講師と学生のための宿舎だったセント・エドマンド・ハウスを選んだ。屋敷は素晴らしく、リーベンシュタイン城よりも快適だった。われわれは美しい庭で討論した。これはイギリス人が初めて多く参加したPIAC会議となったが、何の記録もなく、ジェラルド・クローソン卿がいたことを覚えているだけで、他に誰がいたのか、何人いたのか言えない。それどころか、確かな会議の日程さえもわからない。
それまでのPIACの雰囲気は、当然のことながらケンブリッジで一新した。ドイツ連邦共和国で誕生し、3回の会議がそこで開かれていた時、PIACは、強いドイツ的伝統(「ラインラント的」と言うべきか?)の中にあった。われわれの初代書記長ワルター・ハイシヒの個性は、たとえこの美しい土地で誕生していなくても、学会の性格に深く刻み込まれ、わずかな例外はあったけれども、彼のおかげで、のちの会議すべてが、愉快で形式ばらない雰囲気を持つことになった。
ケンブリッジもわれわれの会議に刻印を刻んだ。午前中のコーヒーと午後の紅茶、晩餐前のシェリー酒と晩餐中のワイン。すべてが、かつての会議がドイツ式だったと同じく、イギリス式におこなわれた。もっと重要なのは、いつのまにか会議の主要言語がドイツ語から英語に代わったことだろう。PIACの名称は最初から英語だったが、ドイツでは、われわれは発表や討論はだいたいドイツ語でしていた。また、この時やや公式的にもなった。セント・エドマンド・ハウスの校長が私たちをシェリー・パーティーに招待してくれ、私は参加者全員をわが家のささやかなガーデン・パーティーに招いた。
会議の性格がさらに変化したのは、第5回会議が1962年6月4~9日にブルーミントンのインディアナ大学で開催された時である。1962年春学期、私はインディアナ大学ウラル・アルタイ学講座(当時はそう呼ばれていた)の教授職を引き受けた。PIACをブルーミントンに招くのが私にとって当然の処置であった他に、この招致が大学にとっても好都合である重要な理由があった。
ハーマン・ウェルズ学長のもとで、インディアナ大学は協力して国際的な学問分野に努力を払っており、アルタイ学における国防教育センターを学内に設立することを望んでいた(つまり、私が招かれたのはこのためである)。アルタイ学で有名になることが大学の関心事であり、私こそが適材適所であると示すことは私の利益になった。多数のヨーロッパ人の存在なしでは成功したPIACにならないことは明らかだったが、同時に、米国に短期間旅行するために、ヨーロッパ人やアジア人が喜んで金を出したりしないことも明白だった。必要な財源は大学が提供した。34名の参加者のうち18名が合衆国以外、オーストラリア、デンマーク、フィンランド、ドイツ連邦共和国、英国、オランダ、ハンガリー、イタリア、日本、ポーランド、トルコから参加した。
当然、すべての参加者の旅費、宿泊費をまかなうために、補助金が必要だった。これは、この会議の特別な目的のために、インディアナ大学と契約を結んだ米国教育省が提供した。苦労のかいは大いにあった。アルタイ学およびこれに関連する分野の学界と米国教育省の中で、インディアナ大学で何かすごいことが起こっていると知れ渡った。一方、大学は、言った通りに、私がそういう任務のやり方とコネを知っているということを認めた。
これを読んでいるほとんどの読者にとってたいした意味はないかもしれないが、当時鉄のカーテンの向こうで仕事をしている学者をブルーミントンに連れてきたのは、非常な成功だった。PIACが開かれた当時、「ハンガリー問題」はまだ米国の懸案条項(アジェンダ)だったので、2人のハンガリー人学者(シュッツとツェグレーディ)が米国を訪問するのは簡単ではなく、ハンガリーとのよい関係を必要とした。常に慎重なルイ・リゲティが反対しないでいてくれたので助かった。3人目の「鉄のカーテン」の学者、ポーランドからのアナニアス・ザヤンチコウスキの旅行準備はもう少し楽だった。
ブルーミントン会議では二つの重要な進展があった。私は、5年任期のPIAC書記長に選出された。議事録で使われた誇張した表現を引用すると(最後に教育省に転送しなければならないので、独特の文体で書かれた)、会議の参加者は「今後5年間PIACの中心を米国に置くことにより、新選の書記長が米国と世界におけるアルタイ学に新たな刺激となるような、具体的な計画を遂行する公算が大であることを期待するものである」。もちろん、そのような規模では何も起こらなかったが、PIACがその分野の学問を後援する助けとなったとは言ってもいいだろう。
二つ目の進展は、インディアナ大学が第5回会議を記念して、インディアナ大学アルタイ学賞を設けたことである。この賞は、PIACが「アルタイ学の進展に顕著な功績があった」と認めた学者に毎年メダルを授与するものである。最初の決議で多くの条件が与えられたが、ほとんどは実行不可能だった。二つだけは、いくらかの修正ののち、時の試練を越えて生き残った。一つは「各会議で4人の委員(できれば過去のメダル保持者)が選挙資格のある者から選ばれる。委員会は2人から4人の、メダルを受ける価値があると思われる学者の名前を次の会議に提出する義務がある」。二つ目は、「選挙資格者は、アルタイ学の分野に誠意を持って対している学者で、過去にPIACに参加したことがあり、選挙が行われるPIACに参加している者」という条件である。
授与されるメダルにはインディアナ大学の印章が刻まれた。最初の3つのメダルは銅だったが、その後は純金である。最初の受賞者は、モンゴル学に対するその顕著な功績を表彰して、ベルギー生まれの宣教師で、米国で隠退生活を送っていた、アントワーヌ・モスタールト神父であった。彼は、1963年ヘルシンキで開かれた第6回会議の席上、欠席のまま受賞した。
メダルを授与するための委員会に関する最初の規定が実際的でないことは、やがて明らかになった。1967年英国マンチェスターで開かれた第10回会議で、第一の条件は次のように修正された。「賞の候補者を推薦する委員会は、その時の会長と職務上の書記長と、毎年選挙で選ばれる3人の委員とで構成される。」マンチェスターでのこの決定は時の試練を経ても有効で、今なお議事録を律している。PIAC「家族」の間では、インディアナ大学アルタイ学賞は普通「PIACメダル」と呼ばれているので、私も本論の中ではこれに従う。
1962年にPIACが獲得したより形式的なわく組みは、インディアナ大学の寛大さのおかげで、それまで名前にしか存在しなかった「常設Permanent」という概念が、文書を保管し回状を送付するためのオフィスができて、事実になったことである。1963年の第6回会議はペンティ・アアルトを会長としてヘルシンキで開催され、1964年の第7回会議はカール・ヤーンを会長として、オランダのアルンヘムの近くのデ・ピーテルスベルフ会議中心で開かれた。この時の主題は「古代アルタイ文明における馬」だった。参加者はのちの会議に比べると非常に少ない36名だった。1965年の第8回会議は再び創設者ワルター・ハイシヒを会長として、ボンに近いヴァールシャイトのライン河畔で開かれた。1966年の第9回会議はイタリアの美しい街ラベッロに移った。アレッシオ・ボンバチ会長に、4時間の昼休み(シエスタ)はPIACには長すぎると納得させるのに私は苦労した。この会議は、ナポリの雰囲気と、陽気で魅力的な会長の性格を反映して、まことにナポリ風だった。開会式は、最近修復したばかりでまだ神に捧げられていないトロの聖ジョバンニ教会で行われた。33名の参加者の中に2人のロシア人ナシロフとテニシェフがいた。ラベッロ会議は、私の非凡なアイルランド人秘書デアドルを感動させ、詩作に駆り立てた。
ナポリの海岸をあなたはぶらぶらしながら
昔の「あれこれ」について議論をしている
奴隷の私は雄々しくあなたのために準備をする
こんな会議はかつてあったためしがない
4年間私は勇敢に奉公してきた
だからどうか心に留めて置いてください
私がそこに物体として存在することができなくても
私の精神はずっとあなたとともにあることを
私の暗黙の了解のもと、彼女は1966年7月発行された第1回PIACニュースレターに、この一編を挿入したのである。
1967年6月26~30日、マンチェスターでジョン・アンドリュー・ボイルが開いた第10回会議で、私は次の5年間の書記長に再選された。会議に続く7月10日に、私はボイルに「これまでで最もまじめなPIACだったことは疑うべくもなく、10周年を記念するのにまことにふさわしい」と書き送った。
1968年の第11回会議は、デンマークのホルスホルムで初めての女性会長イベン・メイエルが開催した。ソ連から学者が参加するのは二度目で、ツングース言語学者のチンチウスとトルコ学者のバスカコフはどちらも名声が高かった。チンチウスは1971年にPIACメダルを受賞、バスカコフは1980年に受賞した。
まじめな話題に移る前に、ちょっと思い出話をさせてほしい。ソ連の学者たちの参加は、大いなる嬉しい驚きだったが、どうやってデンマークに来る許可を得たのか私にはわからなかった。彼らの話はこのようである。会議の招待状にはもちろん「王立」という言葉が入っていた。もしかして王立アカデミーのことだろうか? 陽気だけれど内気なロシア婦人のチンチウスは、党の高官に急いで見せて、デンマークに行きたいと思うけれどどうすべきかと訊ねた。官僚は型通り処理しようとしたが、誰一人デンマークのような中立国からの何か「王立」の招待を拒絶する責任を取りたくなかった。それで、彼女は行くように命じられた。しかし、全く理由のないことではなかったが、官僚は老婦人を完全には信用しなかった。逃亡はしないだろうが、ソ連とソ連学界の権威ある代表としてふさわしくないかもしれないことを怖れたので、同じく招待を受けており、男であるバスカコフが、チンチウスの付き添いとして行くよう命じられたのである。彼らは2人とも大いに楽しんだ。
ホルスホルム会議は、デンマーク・ビールの大醸造所がスポンサーになり、歓迎会では大盤振る舞いのスポンサーの産物が、いわく言い難い、実に愉快で和やかな雰囲気を醸し出した。フィンランド人レセネン、ポーランド人ザヤンチコウスキ、ロシア人バスカコフがジョッキを高く掲げ、声を張り上げて、彼ら3人の生まれ故郷の、同じ帝政ロシア時代の古い国歌をともに唄った光景を、私は決して忘れない。それを見聞きしながら、私はPIACを続けてきて報われたと感じた。
私自身に政治的野心はなかったけれど、それぞれの国の政治体制とは無関係に学者が集まれるよう、私は必要な限り、異なる政治体制の橋渡しをする努力をした。1950年代の初めから、かつての名称の国際東方学会(3)のより広い領域で、私はこれにかなり成功していた。「共産圏の」学者をPIACに参加させることに私はさらに熱心になった。なぜなら、ロシア人やハンガリー人やポーランド人のアルタイ学における功績は偉大なものがあったからである。この偏見のなさはPIACメダルの授与に反映している。最初の六つのメダルのうち3つは共産圏の学者に授与された。1つはモンゴル人、2つはハンガリー人にだった。
最もかたくなな社会主義国から敵陣突破が始まった。その時東ベルリンで教えていたハンガリー人トルコ学者ジョルジ・ハザイの手柄だった。彼がどうやって、教条主義的でお堅いことで悪名高いドイツ民主共和国科学アカデミーの共産主義指導部に、「アメリカ風の」PIACをベルリンに招待することを納得させたかは、私にはいまだになぞである。彼が回想録で秘密を明らかにしてくれることを願うだけだ。すぐれた手腕と勇気と、それから冒険心が、そうした行動を考えるためだけにさえ必要である。1968年6月、ホルスホルムのPIACのあとハンブルグで数日滞在していた私のもとに、予備調査に東ベルリンへ来るようにというハザイからの招待状が届いた。
冷戦時代特有のかたよった思考態度をよく知らない人々のために、私はまた思い出話をせざるを得ない。当時まだいくつかの国籍は合法ではなく、私のフランス国籍もだった。私は米国の永住者だったが、社会主義国を訪ねるときは常に、出発前に、出入国・帰化管理局の許可を得る必要があった。それは単に形式で、許可が得られなかったことはなかったが、問題は、その夏社会主義国を訪ねるつもりはなかったので、1968年6月ハンブルグで許可を持っていなかったことだった。どうやって東ベルリンへ行くか? 隠密作戦の経験はいくらかあったので、私のパスポートにドイツ民主共和国のスタンプが押されない限りは、喜んで危険を冒すつもりだった。手短かに話そう。私はドイツ民主共和国に車で入国し出国した。厳格な警察が管理しているいくつかのホテルに泊まったが、私のパスポートには旅行の痕跡はつかなかった。米国に戻る時も当局との間に何の問題もなかった。ハザイがちょっとした奇跡を行ったのだ。われわれはこの冒険を本当に楽しんだ。
準備の段階で、西ドイツの学者の存在は微妙な問題と思われたが、彼らが東ベルリンに来るのに、いかなる障碍もないという保証を私は得たし、実際、比類なきアンネマリー・フォン・ガバイン、われわれの愛すべきマリアム・アパもやって来た。私は1937年ベルリンで初めて彼女に会ったが、その頃彼女は熱烈なヒトラーの信奉者だった。けれども、年月をへた今では、誰も彼女の心得違いを攻撃しなかった。彼女は害を受けることもなく、その仕事における無邪気な率直さには、どんな批判も太刀打ちできなかった。実際、彼女の政治的な純真さは感動的ですらあった。PIACの日程は偶然、ウィリー・バンの生誕百周年にあたり、コノノフがトルコ学における彼の役割を評価し、マリアム・アパはかつての先生についての思い出を語った。
会議参加者は非常に多くて、150名ぐらい、当然かなり正式なものだった。われわれは一つ屋根の下には泊まらず、別れて食事したが、何回か非常に盛大なレセプションがあった。純粋に学問的水準から言うと、おそらくソ連からの大量の参加のおかげで、第12回会議はかつての会議の中で最高水準だった。素晴らしい会議録がこのことを証明している。
設立当初から、PIACにはフランスからの参加がなかった。この事実をハイシヒが問題にして嘆いたので、私が小論文を書いて、その理由を説明しなくてはならないかと思うほどだった。それで、5人のフランス人学者がベルリンにやって来たのは、鉄のカーテンの向こうからたくさんの学者が会議に参加したのと同様、喜ばしいことだった。遅れてやってきたせいで熱狂した結果、PIACの第13回会議はフランスのストラスブールに招かれた。もちろん私は特別嬉しかった。私にとっては一種の帰郷だったし、かつて一緒に勉強した仲間たちと新たな関係が結べることを期待したのである。
1970年6月ストラスブールで開かれた第13回会議が大失敗だったので、私は本当にがっかりした。私が昔ジャン・ドニの授業で机を並べた魅力的な婦人イレーネ・メリコフが会長だったのだが、彼女はPIACについて何の考えもなかった。彼女が初めて参加した唯一のPIACは、全くありきたりな会議のやり方を踏襲した第12回会議だったので、これがストラスブール会議のモデルとなった。また、ベルリンでソ連からの多くの参加者を見たので、彼女は当時の政治的実情を完全に誤解し、ソ連の学者がストラスブールに来る許可が下りるものと決めてかかり、その上、アゼルバイジャン出身の婦人に会議を主催させた。さらに、彼女が選んだ会議の主題「アルタイ系民族の宗教的および宗教がかった伝統」自体が、彼女が参加を重視していたソ連の学者を遠ざけた。
ストラスブールでは、参加者をとりまく雰囲気は時として友好的なものではなく、純粋に学問的とは限らない険悪な議論もあった。会議の最中、たくさんの猛烈な苦情が私のもとに届き、何人もの会員が憤慨した手紙を寄越した。そのほとんどが、われわれの会議の将来に有益な提言だった。PIACニュースレター8号に、ハザイ、ハイシヒ、ホフトハウゲン、ヤーン、ヨハンセン等の提言を私は再録した。彼ら全員が、参加者の数を制限することを主張していた。ここで、カール・ヤーンの提言を引用する。
「専門家たちと、彼らが推薦する若い研究者を招待することで、参加者の数を制限する方がよいと私は思う」
もっと婉曲な表現で、ワルター・ハイシヒはこのように述べた。
「今やPIACは再び大きな学会に成長したのであって、その結果、当初の考えは背景に退いたと言っても過言ではない」
「古参」だけが「大学会症候群」に向かう進化に気づいて不満だったわけではない。「PIAC若手会員」を自称するエヴェン・ホフトハウゲンも同様に、誰をPIACに招くかを決定する委員会を創るべきだと提案した。
彼らやその他の多くの人々の意見と私の個人的経験によって、何年かで、私は望ましくて実行可能な妥協点を見つけた。今日まで、PIACの招待状は、さまざまな組織が無料で、あるいは代金引換で提供する住所録によって送られることはない。招待状は、以前の会議に出席したことがあるか、または過去の参加者によって推薦された本物の学者だけに届くのである。
それはさておき、ちょっと思い出話をしよう。1970年2月、私は重い心臓発作に襲われ、ストラスブールの会議までに完全に回復していなかった。私は会議の間、明らかにストレスを感じており、いつもほど平静ではなかった。さらに、PIACと直接の関係はなかったが、厄介な事件があった。ストラスブールの夜の盛り場で、1人の外国人参加者(フランス人でない)が飲み過ぎて暴れた。警察が到着した時、彼は拘束に物理的に抵抗するという重大な過ちを犯した。もちろん警察署では、彼はそんなにひどくはなかったがおとなしくなる程度になぐられた。私は警察に出頭して、警察官の行為を訴えないから拘束を解いてくれるよう折衝する羽目におちいった。困難な交渉だった。
次の年PIACはハンガリーに移動した。名目上はリゲティ会長のもと、実際はアンドラーシュ・ローナ・タシュが運営して、第14回会議がセゲドで開かれた。ローナ・タシュと私の共通の先生である、つねによく気の付くリゲティが後ろから見ているという難しい仕事だったが、ローナ・タシュは、PIACの伝統に通じており、見事に責任を果たした。
私は参加者リストを持っていないが、立派に出版された会議録を見ると、それまでの中でもっとも「国際的な」会議だったようである。自由な社交と、よい「コンフェッションズ(告白)」(これぞわれわれの会議の神髄である)と、あまり退屈でない儀式。われわれの会議の最中の8月24日、ケレシ・チョーマ学会(ハンガリー東方学会)がヨーゼフ・アッティラ大学の講堂で開かれ、バスカコフ(ソ連)、ジェラルド・クローソン卿(英国)、ギョクビルギン(トルコ)、私デニス・サイナー(米国)が学会の名誉会員に選ばれた。
私はすでに何度もPIACニュースレターについて言及してきたが、この辺できちんと言っておくべきだろう。会議と会議の間の期間を埋めるささやかな出版物の着想は、デ・ピーテルスベルフ(オランダ)で開かれた第7回会議で生まれたが、翌年、創設者ワルター・ハイシヒが会長となったヴァールシャイト(ドイツ)の会議で、さらに絶対的な命令となった。ごくささやかな印刷物(コンピューター以前の時代だ)が1966年7月初めて発行された。それ以来、だいたい年1回の間隔で、主としてPIACの歴史を記録する目的で、ニュースレターは発行されてきた。私の自由になるこれらの印刷物なくして、このエッセイを書くことはできなかっただろう。
カール・ヤーンが退官し、ユトレヒトからウィーンに移った。彼はその近くのシュトレーベルスドルフで、1972年8月7~11日、第15回会議を主催した。中華民国(台湾)から3人参加したのは、われわれの学会が拡大したということで大歓迎だった。その時にはソ連からの参加は当たり前になっていた。アネ・ナウタ(オランダ)の提案で、今後の会議の招待状は、会長と書記長連名で送ることが決まった。それまでは会長(会議の主催者)だけが署名していたのである。この決定は記録をつけることを楽にした。同時に、私は向こう5年間の書記長に再選された。
トルコ文化研究学会がアンカラで開催すると発表した第16回会議は、同時にトルコ共和国建国50周年を記念するものだった。モンゴル学者のアフメト・テミルが会長となって1973年10月21~26日に開かれた会議は、大宴会と公式演説には事欠かなかった。トルコからの招待は、わが会員や私自身にとっても、おおむね喜ばしい。トルコ人学者はずっとPIACに参加していたし、アフメト・テミルを含む4人はすでに第2回会議に参加していた。
彼らPIACメンバーは、しかし残念ながらアンカラでは、トルコ語でトルコ人に対してトルコ学(チュルク学ではない)の報告をする機会を得ようとする、多くのトルコ人学者の中に埋没していた。100人の参加者は、PIACの目的からはあまりに多すぎたし、われわれの会議を国際トルコ学会にしようとする者も多すぎた。わがトルコ人仲間が何人も、この態度に不満を表明したことを注記しておかねばならない。
PIACは、続く3回の会議で、その本来の形を取り戻した。1974年の第17回会議は、ワルター・ハイシヒが主催し、再びラインラントのバート・ホネーフで開かれ、1975年の第18回はブルーミントンに戻り、1976年の第19回はアウリス・ヨキが会長となってヘルシンキで開かれた。
第20回会議は、1977年8月15~19日、ナウタが会長となってライデンで開かれた。私は次の5年間の書記長に再選された。ニュースレター12号の序言で、私はこう述べた。「PIACと違って、私は「常設」ではない。私の継承問題について少しは考えた方がいい」。私の再選は「他に選択肢のない」あきらめを反映していたのかもしれない。私はPIACが独立を保つように精力を注いできたし、「ひんぱんな会議で旅費や電話代が高くつく管理機構なしでは運営できない国際委員会などに、書記長は妨害されるべきではない」と思っている。私はずっと言っているのだが、PIACの運営に必要なのは、しっかりした地盤があって、PIACを優先することのできる中年の書記長である。私は過去に一度も会議を欠席したことはない。
1978年の第21回会議は、ボイルが再びマンチェスターで開催する任を負った。その数ヶ月後の11月19日、彼は突然世を去った。彼は、われわれ仲間から本当に愛され、尊敬されていたので、今まででたった一人の例外として、1979年のPIACメダルを追贈された。
ベルギー国籍でシカゴ大学で教えていたリュック・クワンテンが率先して、第22回会議は、ベルギーという「新しい」国に移動した。シャルル・ヴィレメンが名目上の会長となって、1979年5月27日~6月2日、われわれはゲントに集まった。
おそらくわれわれの会議の独特の魅力のために、みんな喜んで主催するだけでなく、何年か休んで元気になったら、また主催する気になるようだ。創設者の一人で、第7回(1964年)と第15回(1972年)を主催したカール・ヤーンは、退官後の1980年、第23回会議を、ウィーンの近くのシュトレーベルスドルフで開催することにした。ヤーンと私はよい友だったし、彼の無尽蔵のジョークの貯蔵庫についてはすでに言及した。しかし、シュトレーベルスドルフで、彼は政治的、私は学問的見地から、われわれは鋭く対立した。論点は「自由ヨーロッパ放送Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)」の存在だった。
インディアナ大学ウラル・アルタイ学科の私の優秀な学生が何人も、猛烈な反共産主義の「自由ヨーロッパ放送」に就職していた。冷戦時代、私はこの種の組織のたいていの活動に賛同しなかったが、学生たちがしていたのは、現代の中央アジア諸言語の調査や地域研究で、彼らを会議から排除する理由は私には見つからなかった。政治的決定は含まれていない。私の場合、PIACにおいてはつねに政治的に中立である。われわれは、共通の学問的興味によって結ばれた学者仲間で、一部の参加者が抱いているかもしれない政治的意見は気にしない。
RFE/RLのスタッフの存在が、彼らがPIACに来られること自体が示しているように、完全に閉じているわけではない鉄のカーテンの向こうからの参加者たちに、迷惑がかかるかどうかが議論された。敵の回し者と接触したということで、彼らが帰国してから被るかもしれないどんな不都合も、彼らの問題で私には関係ない、と私は言った。しかし、もちろん私は、かつての学生たちに慎重に振る舞うように頼んだ。彼らは私の頼みに従った。全てが過去のことになった今、私が取った非政治的立場は誰も傷つけなかったことは明らかである。PIACは制限を受けることなく開放されていた。
何年もの間、PIACの会員資格は、正式にというより暗黙の了解によって、PIACメダル選定委員を選挙する投票権と同一視されていた。第5回会議での決議案により、選挙権は、過去のPIACに出席し、選挙の時に出席している人々の特権だった。この決議案から18年もたつと、過去に一回出席しただけでは、PIACの活動にたいへん熱心とは言えず、そのような偶然の出席者に投票権を与えるべきでないという感情が出てきた。グンナル・ヤーリングが豊かな政治的経験にもとづき、今後は3回の出席(つまり、過去2回の出席)を投票資格とすることを提案した。彼の提案は可決された。
シュトレーベルスドルフで私は、近代以前の中央アジアのロシア人専門家で、最近イスラエルに移住したユーリ・ブレゲルと出会った。彼は第24回会議を組織することを申し出た。もちろん、私に異存はなかった。1981年8月16~21日、ユーリ・ブレゲルを会長として、第24回会議がエルサレムで開かれた。規模は小さかったが、素晴らしい学識と真心のこもった会議だった。その真心は、イスラエルの旅券審査の無礼とは著しい対照をなしていた。PIACは、開始直前に別の国に変更することだって出来るのだ!
翌1982年6月8~11日、グンナル・ヤーリングが会長になって、シュタッファン・ロセーンの補佐でウプサラで開いた会議で、われわれは25周年を祝った。四半世紀の間にPIAC会議は15の国で開かれた。PIACメダルの授与に関して、ヤーリングはあまり「合憲的でない」不意打ちをたくらんだ。PIACの25周年を記念して、2つのメダルが同時に、2人の書記長ワルター・ハイシヒと私に贈られた。私の事務期間は再び5年後まで延びたが、私はその最後までもちこたえられると思えなかった。実際、私の心臓は非常に悪い状態で、ごく短い距離を歩いただけで胸が激しく痛んだ。PIACの数週間後、私は5つのバイパス手術を受けた。そして私はまだ生きて話をしている。
個人的な話を続けると、賞を受けた時、私はヤーリングに冗談を言った。「ブルーミントンに戻って、私は自分自身にメダルを渡すのか」と。そういうことにはならなかった。この非常に忙しい男は(当時彼はまだ国連事務次長の一人だったと思う)、メダルを私に手渡すというたった一つの目的のためだけにブルーミントンにやって来た。インディアナ大学の当時の学長ジョン・ライアンの主催する、私にとって忘れられないディナーの席で、私はメダルを手渡された。メダルが誰に授与されるかは会議の最中に決まるので、受賞者の名前を刻んだメダルは普通、あとで郵送されるということを言っておくべきだろう。
第22回会議を母国のベルギーで組織したリュック・クワンテンは、今度は自分の大学にPIACを招いた。1983年8月15~20日、シカゴ大学の後援で彼の主催する第26回会議が開かれた。米国で開催されたのは3度目である。服部四郎教授がPIACメダルを受賞し、1983年9月5日、京都大学羽田記念館で開催された「国際クリルタイ」の席上、私が本人に直接渡すことが出来たのは嬉しかった。
メダルの授与式は、第31回国際東方学者会議(正式名称は、国際アジア・北アフリカ人文科学会議)の最中におこなわれた。この会議は多くのソ連の学者たちを招き、われわれの将来にも関係することになった。京都で私は、アルタイ学に大いに関心のある一般言語学者で、偏見がないことが明らかなヴァルドゥルに出会った。私は、将来PIACをソ連で開催したいと彼に申し出た。驚いたことに、ヴァルドゥルはPIACの存在を十分承知していて、ソ連にPIACを招聘することをモスクワで話し合ったことがある、と私に漏らした。そのさい、ハンガリー出身という、私個人の経歴が問題になり、ソ連の学者たちは、ハンガリーに容認されない「亡命者」と協調したくなかったようだ、ということまで、彼から知らされた。しかし、ハンガリーへの照会(誰がどんなふうに?)は、私がその地で「好ましい人物」であることを示したので、政治的にハンガリーの感情を害する恐れは消えたのである。
第27回会議は1984年6月12~17日、クラウス・ザガスターを会長として、ケルン近くワルバーベルクのドミニコ会修道院で開かれた。中心題目は「アルタイ世界の宗教的および宗教的でない象徴性」である。全く主観的な私のメモによると、「今までで一番よいPIAC」だった。それはともかく、この会議には、初めて中華人民共和国からの参加者があった。彼の名前は馬雍と言った。「中央アジアの文明の歴史」刊行を託された国際ユネスコ委員会で、私は彼と知り合った。私はこのプロジェクトで、ソ連と激しく対立して中国人の参加を確保するという特別な役割を演じ、馬は私の援助に感謝した。
馬は、ユネスコ委員会では大声の毛沢東主義者だったが、個人的な会話ではなかなか愛想がよかった。修道院の礼拝堂でクラシックの土曜コンサートがあったので、私は彼に来ないかと誘った。彼はすぐ同意した。私は彼に、翌朝、一緒に日曜日のミサに出る気はあるか訊ねた。彼は同意した。ミサの間、私は彼に典礼の意味を説明しようとしたが、その基本的な原理について彼がよく知っていることがわかった。のちに彼は、PIACが彼の夢の一つをかなえてくれたと私に明かした。ワルバーベルグに来る前に、彼は近くのボン市にある、ベートーベンが生まれた家を訪ねたのだ。文化大革命の恐怖の間、この夢はどんなに深く埋もれていたのだろう? その時私は、PIACのための私の苦労は、馬がベートーベンの生誕地を訪れることができたことを感謝するなら、無駄ではなかったと思った。彼は1985年51歳で亡くなり、私はPIACニュースレター16号で彼を偲んだ。
1984年6月、ワルバーベルグPIACの直後、私はソ連アカデミー言語研究所の招待でモスクワに行った。招待はヴァルドゥルの提案で、私は真心こめた接待を受けた。その後一貫してPIACの支持者となる日本語学者アルパートフがいろいろ手伝ってくれた。私は研究室から研究室へと引っ張りまわされ、多くの重要人物に会ったが、その中に、当時ソ連アカデミー東方研究所言語部門の長だったヴァディム・ソンツェフがいた。
私は、1982年モンゴルで開かれた第4回国際モンゴル学者会議で、すこぶる異なる意見を披露する彼と会ったことがあった。それ以来、彼と個人的な関係はなかったが、ヴァルドゥルとアルパートフのおかげで、ソンツェフは私を快く受け入れた。モスクワ滞在中、私は何度か講演をしたが、その中に、新しくできたばかりの、パキスタンと中国をつなぐカラコルム・ハイウェイを1983年に走った私の旅行の話もあった。ソ連にとって非常に興味があるが、まだ知られていなかった地域である。
モスクワに到着する前、私はカザンからも招待されていたが、典型的なソ連式言い訳でその旅行は中止となり、代わりにアカデミーの負担でウズベキスタンとアゼルバイジャン訪問に変更になった。魅力的で有能な若い男、サーシャ・バルリンが私の世話をしたが、彼とはそれきりだ。あとから考えてみると、モスクワで私が「重要人物」の間をめぐったのは、彼らが印象を話し合って、その後の方針を決めるために必要だったのだろう。
ここで私の旅行の細部を語る必要はないが、このエッセイに関係しているのは、私がインディアナ大学で行政的な仕事をしていることをよく知っているウズベク・アカデミーの何人かと、長い非常に建設的な会話をしたということだ。私の学生が何人もすでにタシュケントを訪ね、滞在していた。はやりの言葉を使えば、化学反応が起こった(機は熟した)のだ。私の新しいウズベクの友人たちとの交流の印象はそれくらいにして、モスクワに戻ろう。6月18日、自宅での非常に楽しい晩餐の席で、ソンツェフは、第29回会議をタシュケントで開くつもりであり、正式の決定は1985年5月に出ると私に言った。
1985年、19年ぶりにPIACはイタリアに戻った。今回はヴェネツィアだった。シカゴでの第26回会議に、ヴェネツィア大学のアンドレア・チラギが現れ、彼流に愛想よく、アルタイ学にとても興味がある、と言った。彼はワルバーベルクに再び現れ、第28回PIACをヴェネツィアに招いた。ボンバチの死後われわれはイタリアとの関係がなくなっていたので、もちろん私は喜んだ。なぜチラギが、彼にとって最後となった会議を骨折って開催したのかは、私にとって疑問のままだ。何年も後に、彼が移った先のウディネで、相変わらずチャーミングな彼に私は会った。会議録はジョバンニ・スターリによって刊行された。
ソンツェフはヴェネツィアの会議にやって来たが、明らかに楽しんでいた。彼が次の会議を開催する任を喜んで引き受けることを、私は驚かなかった。彼が克服すべき困難は、技術的のみならず政治的にもたくさんあった。政治的レベルでは、問題はソ連と西側の関係ではなく、ウズベクの感情を害さないように気をつけねばならないことにある、と私には思えた。技術的レベルでは、当時はEメールもファクスもなく、電話は全く当てにならず、ブルーミントンとモスクワの文書のやりとりに2ヶ月かかることもあったことを、思い出してほしい。ロシア人とウズベク人との間の交渉については私はほとんど知らない。最終的に、われわれの第29回会議は、ソ連科学アカデミー東方学研究所とウズベク科学アカデミー言語学研究所の共同後援で、9月15~21日タシュケントで開催された。ヴァディム・ソンツェフが会長だった。会議の中心主題は「アルタイ系言語を話す人々の間の歴史的文化的接触」である。
拙論「第29回PIAC会議の序論」は、『ウズベク語と文化』の特別号に掲載された。英語とロシア語での開会の挨拶に加えて、学問は超国家的supranationalであるだけでなく国際的internationalであるべきだと、私は強調した。たいして独創的な考えではないが、タシュケントではほとんど表明されなかった意見である。残念なことに、ほとんどのトルコ人参加者は、すべてのトルコ系民族を結びつける兄弟説を強調するため、この機会を利用した。それがどんなことを意味しようと、この有無を言わさない「兄弟関係」と、私は争うつもりはないが、そういう問題はPIACの集まりに侵入すべきではないとその時思ったし、今もそう考えている。
もう少し明るい気分で、会議運営の難しさを描写する助けとなるような逸話を話そう。すでに述べたように、インディアナ大学アルタイ学賞の受賞者を決める委員会は、選挙資格のある会員の無記名投票で選ばれる。ウズベク人参加者たちはこの事実をしぶしぶ認めたが、ソンツェフを通じて投票の仕方を「指図」しようとし続けた。風向きが突然変わって、ちょっとうろたえたソンツェフは、「もし委員会に彼らの一人が入らなければ、現地の学者たちが非常に腹を立てるだろう、どうしよう」と私に告げた。私は答えた。「それでは、シカゴ式投票スタイルからロシア式にしよう」その結果みんなが満足し、ウズベク人学者が順当に選ばれた。単純な解決法だ。有権者は比較的少数で、銘々が投票用紙に三人の名前を書く。当然、票はたくさんの名前に割れる。それで私は、できる限り多くの有権者と長話をする間に、三人のうちの一人はXに投票するようにと勧め、彼が正当に当選したのである。ウズベクの名誉は守られたし、ソンツェフの権威も増した。もちろん、私が候補者のために圧力をかけたのはこれが初めの終わりである。
私はつねに、PIACにソ連の学者を参加させることを大いに重視している。タシュケントでの開会の挨拶で、私はこの理由を公に述べた。「アルタイ学の領域、中央アジアと内陸アジアの現在と過去の研究において、ソ連の学問は特別な地位を占める。アルタイ系の人々の歴史が刻まれている地域の大部分が、現在ソ連の領域にあるからである。」
1987年第30回会議で、PIACは本部のあるブルーミントンのインディアナ大学に帰った。13の国から54人が参加し、私はさらに5年間の書記長に再選された。当然、アメリカ人参加者が最多(25人)だったが、大多数は地元の人だった。もっと大切なのは、中華人民共和国から4人ブルーミントンに来たことで、竹のカーテンは少しずつ上がっていた。
そろそろPIACの財政について述べる時期だろう。1962年以来、インディアナ大学は寛大にも、事務用品と郵送費と秘書といった基礎経費を出してくれていた。会議の経費を準備するのは主催した会長の任務だった。ヨーロッパに住む大多数の会員にとって、他の地域(イスラエルや米国やソ連)で開かれる会議への旅費は高額すぎた。1989~90年の政治的大変動までは、社会主義圏の同僚が、旅費をまかなう外貨を工面することは難しかった。1970年代半ばから、ハンガリーやポーランドへの旅行許可は簡単に得られたが、会議の財源を見つける任務はつねに会長の責任で、会長は参加者から徴収する料金で費用の大部分をまかなった。補助金はだいたい、社会主義圏からの参加者の旅費と宿泊費に使われたが、前年の会長と書記長は招待することが伝統となった。
アルタイ学に熱心な社会主義諸国は、PIACを招くことによって、外国の学者の好意に報いようとした。なぜだか分からないが、ポーランドだけがそうしなかった一方、1988年ドイツ民主共和国(東ドイツ)が二度目に招いた。ハンスペーター・フィーツェが会長となって、第31回会議が、まだ当時は東ドイツだったワイマールで開かれた。ベルリンのフンボルト大学とドイツ民主共和国科学アカデミーが会議を後援したが、その直後にこれらの組織はすさまじい変化をこうむった。
1989年、ベルント・ブレンデモエンが会長となって、第32回会議がオスロで開かれた。こうしてわれわれを受けいれた国々の長いリストの中に、ノルウェーも加わったのである。偉大なロシア人トルコ学者バスカコフは、参加できなかったが、自分が作曲した滑稽な「PIAC賛歌」の歌詞と楽譜を送ってきた。アフメト・テミルはこの曲にトルコ語の歌詞をつけた。PIACのまじめな歴史にそんなくだらない事を書くなんてと眉をひそめるとしたら、そういう気楽な事が、まじめな学者のこの独特の集まりの芯となるものであると返答しよう。
オスロのあと1990年の第33回会議はハンガリーに帰った。今回はブダペストで会長はアリス・シャールキョジ、1968年以来久しぶりの女性会長だった。彼女は、社会主義から別の体制へと変わるハンガリーの混乱をうまく乗り切った。会議の中心主題は「アルタイの信仰と実践」である。シャールキョジはバーバラ・ケルナー=ハインケレにバトンを渡し、彼女が1991年ベルリンで第34回会議を開いた。その直前のドイツ統一と「ベルリンの壁」の崩壊で、かつて1969年第16回会議が開かれた時と、情況はすっかり異なっていた。かつての西と東のドイツ人学者が自由に交流しているのを見るのは嬉しかった。この街の素晴らしいアルタイ学の伝統、ごく少数言及するだけでも、バン、ルコック、ミュラー、アンネマリー・フォン・ガバイン、エーリヒ・ヘーニシュなどの学者が活躍したことを思い出さずにはいられなかった。中心主題は「アルタイ世界の王権の概念」である。
東アジアの学者たちは、PIAC会議のごく初期から参加していたが、旅費が高くつくため数は少なかった。その代わり、地方的会議が組織された。先導したのは、日本若手アルタイ学会、いわゆる野尻湖クリルタイを組織した日本の研究者たちである。私の知る限りでは、1976年7月のその第3回会議で、PIACと張り合うためでなく、これを補完するために、東亜アルタイ学会(EAAC)の創立を決めたという。
EAACの初代書記長は山田信夫で、会議は毎年、たぶん日本で開かれたのだろう(訳者注:第1回は日本、第2回は台湾、第3回は韓国で開催された)。しかし、1971年、第4回会議は台湾で開かれた。私は「学者顧問」として参加するよう招かれ、二人の主催者、スチン・ジャクチドと陳捷先の行動力に大いに感銘を受けた。陳捷先は、1979年12月26日~1980年1月2日、台北で開催された第5回EAACも主催した。
われわれの台湾人仲間は、彼らの言うところの中国辺境地域研究の進展にますます興味を持つようになり、その中の何人か、主としてジャクチドと陳は、1976年からわれわれの会議の常連メンバーになった。中華民国でPIACを開催するのは、なみなみならぬ財政的かつ政治的困難があることを知っていたが、私は彼らにそうしてほしいと熱心に励ました。陳捷先は奇跡を行い、第35回会議は台北で開催された。みなが喜び、ある者にとっては驚きだったことに、中華人民共和国から数名の学者が参加した。ふたたび、小さな分野だけれども、PIACが相反する政治勢力の架け橋となることができたのである。会議は、国立台湾大学と連合報文化基金会国学文献館の共催で、参加を希望した本来のPIACメンバー全員の旅費に補助金が出た。この会議で、私はさらなる5年間の書記長に再選された。
私は、次の会議はメンバーが参加しやすい場所で開かれる(つまりヨーロッパに戻る)ことを望んでいたが、めったにない機会として、1993年第36回会議は、カザフスタンのアルマ・アタ(当時そう呼ばれていた)で開催された。カザフ科学アカデミー東洋学センター長カジベク(エルデン・カジベコフ)が会長となり、カザフスタン共和国科学アカデミーが後援した。開催の仲介をした功績は、ロシア科学アカデミー東洋学会副会長ディミトリー・ワシリエフのものである。会議を組織するにあたっての困難は計り知れなかった。通信はほとんどモスクワを経由せねばならず、ファクスも当てにならなかった。Eメール以前の時代である。会議が、当時は非常にエキゾチックな場所と考えられていたところで開催されるというニュースは、それまでPIACに何の興味も示さなかった、見知らぬ雑多な人々を呼び寄せた。われわれの仲間にとって幸いなことに、会議が終わると、彼らはわれわれの前から消えた。個人的には、私の滞在中のハイライトは、カザフ言語学の第一人者スメト・カネスバエフの家での、夜まで続いた、愉快な長い昼食だった。
ほとんど四半世紀ぶりに、1994年PIACはフランスへ帰った。ジャン・リシャールが会長となって、第37回会議は、パリの近郊シャンティイで開催された。中心題目は、「中央ユーラシアとその西方世界との接触」である。
その時まで、PIACは19ヵ国に招かれていた。岡田英弘は、妻の宮脇淳子とともに過去の数多くの会議に参加していたが、日本が20番目のPIAC開催国になるべきであると確信していた。彼が会長となって、第38回会議は、アルタイ学の発展に大いに貢献してきた国で初めて開催された。会議は1995年8月7~12日、東京の近くの川崎で開催された。まことに残念なことに、同じ年の会議の前に、二人の偉大な日本人アルタイ学者、服部四郎と村山七郎が亡くなった。
翌1996年、第39回PIAC会議はハンガリーの、第14回会議のあったセゲドに戻った。会長はアールパード・ベルタである。中心題目は「内陸アジアとヨーロッパの間の歴史的・言語的相互作用」で、ハンガリー人がこの地を征服してから1100周年という記念の年を祝うのに、最もふさわしいテーマだった。ハンガリーで開催される3回目の会議だったが、主催者たちが、政治的に不適当であると考えて、「征服」ということばを使わないよう努力していたことを記す時、私は苦笑せざるを得ない。
PIACの第40回会議は、1997年6月2~6日、アメリカ合衆国ユタ州プロヴォで、デヴィド・ハニー会長のもとで祝われた。中心テーマは「歴史的・文化的・言語的なアルタイ系の近縁性」である。ビジネス・ミーティングで、さまざまな議論をしたあと、われわれの会議の投票権の規則を変えることが満場一致で決まった。第23回会議で採用された規則「投票権は、その会議を含めて、少なくとも過去3回のPIAC会議に出席している者に与えられる」は、修正された。これ以後、過去2つ以上の異なった国におけるPIAC会議に、3回以上参加した者に投票権があることになった。この変革の妥当性は、PIACの長い歴史において、会議を3回以上開催する国ができ、自国で開催された会議にしか出席しない者もでてきたという事実にもとづいている。経験も少なく、たぶんPIACの活動にあまり興味を持っていないそのような臨時の参加者は、歓迎するけれども、投票権は持つべきでないと思われたのである。よいか悪いかは別にして、私は再び次の5年間の書記長に再選された。
1998年の第41回会議は、ユハ・ヤンフネン会長のもとで、1963年と1976年の開催地ヘルシンキで再び開かれた。第42回会議は、PIACのがこれまで行ったことのないチェコ共和国のプラハで開かれた。会議を後援したのは「自由ヨーロッパ放送」で、会長はチャールズ・カールソンだった。実際、時代は変わった。1980年には、その組織で働くPIAC研究者を承認するのが一苦労だったことは、前述した通りである。2000年の第43回会議は、以前1979年に開いたことのあるベルギーに帰った。会長はアロイス・ヴァン・トンゲルローで、ラナケンの近く、非常に感じのいい小さなピーテルスハイム城にわれわれは宿泊した。中心テーマは「アルタイ世界のこの世とあの世、および黙示録概念」で、アルタイ学の創設者であるベルギーと関係のある二人の神父シャルル・ド・アルレ(1899年没)とヴィリ・バング・カウプ(1934年没)を記念して捧げられた。
2001年の第44回会議はある意味の里帰りだった。PIACが創設されたラインラントの、しかも、1984年第27回会議が開催されたワルバーベルクのドミニコ会修道院で開かれた。会長はヴェロニカ・ファイトで、参加者にとって最大の喜びだったのは、PIAC創設者ワルター・ハイシヒに会えたことである。
アリス・シャールキョジ会長のもとで、2002年の第45回会議は、1990年以来再びブダペストで開かれた。信じられないことに、私は書記長に再選された。もし任期の最後までいるとしたら、私は91歳だ。PIACの古参メンバーは、私の後継問題にもっと注意を払うべきだと、私は強く要請する。私は、PIACのデータベースをきちんと移転するのに全力を尽くしたし、インディアナ大学がアルタイ学賞を授与するという素晴らしい伝統を継続するための措置を、すでにいくつか取ってある。
以上、年一回旧交をあたため、新しい友人を歓迎する、志を同じくする者の学問的な集まりにふさわしい率直さで、私はできるだけ飾らずに自分の話をした。PIACがさまざまな国家や体制の政治的な違いを超越することができたおかげで、学問的な環境において正当に評価されることをつねに必要とした、閉塞状況の同僚たちに、いくらか助けになったことは、この活動のうれしい副産物だった。
PIACの歴史は幸福な歴史である。摩擦はめったになく、激することは決してなかった。私がいつも「どんなことがあっても友達だ」と言っている仲間たちの、私への変わらぬ信頼と、しょっちゅう、いろんなやり方で示してくれた愛情に、心より感謝している。そして、1962年以来、PIACを保護し、間接的または直接的に財政援助をしてくれた、わがすばらしいインディアナ大学の歴代の当局者たちに、心よりの謝意を表するものである。彼らはひとまとめにして、私がいなくなったあともずっと続くはずの「インディアナ大学アルタイ学賞」を受ける価値がある。
注
(1) 本稿は、PIAC Newsletter No. 27, 2002に掲載された、Denis Sinor, Forty-five Years of Permanent International Altaistic Conference (PIAC) (History and Reminiscences)の全訳である。ほぼ半分割愛した抄訳は、『東方学』第106輯(2003年7月発行)の「内外東方学界消息欄」に掲載された。サイナー先生は、本文にある通り、PIAC創設時のメンバーの一人であり、第4回会議から書記長の任に就いて、以来5年ごとに書記長に再選されて、このエッセイの書かれた87歳に至った。その後、先生は5年の任期をまっとうされて、91歳を迎えられ、2007年7月、ロシア連邦タタルスタン共和国カザンで開催された第50回会議において、出席はかなわなかったが、ビデオレターで、自ら書記長引退を宣言されたのである。次の書記長には、サイナー先生の希望通り、ベルリン自由大学を退官したばかりの、バーバラ・ケルナー=ハインケレが選ばれた。サイナー先生のこのエッセイは、その半生をPIACに捧げてきた先生の遺言のようなものであると訳者は理解している。サイナー先生は、2011年1月12日、逝去された。享年94歳であった。
(2) Altaic Affinities, the Proceedings of the 40th meeting of the Permanent International Altaistic Conference, edited by David Honey and David Wright, Indiana University Uralic and Altaic Series vol.168, Bloomington, Indiana, 2001.
(3) 第一回は日本、第二回は台湾、第三回は韓国で開催された。
原注
1 PIAC Newsletter No.3 (1968), p.3. chiarman(会長)は、やがて世間的な通りのよさからpresidentに換えられた。
2 私が書いたカール・ヤーン追悼文は、PIAC Newsletter 16 (1986), pp.3-5に掲載された。
3 PIAC Newsletter 13 (1982), p.5.参照。
4 1873年に始まった会議は、29回まで国際東方学者会議という名前だった。1973年にパリで開かれた第29回会議で、フランス人が多数を占める、きわめて政治的な顧問委員会が、信じられないくらい不体裁で文法的に不正確な「アジア・アフリカ人文科学会議(CISHAAN)」という名称に変えた。第31回会議の際、賢明なる山本達郎会長のもとで常識が勝利し、「国際アジア・北アフリカ研究会議(ICANAS)」と名称が変わった。
5 私の85歳記念論集に書かれた最高に親切で思いやりのある一篇の中で(Altaica V, Institut Vostokovedeniya RAN, 2001, pp.9-13)、アルパートフ教授はこのタシケントPIACについて異なった見地から述べている。
6 英語原文は、のちにPIAC Newsletter 17 (1987), pp.4-8に再録された。
7 タシケントでトルコ人参加者がトルコ語で発表した論文はThrk dili araÕt2rmalar2 y2ll2—2 Belleten 1986に掲載。
8 PIAC Newsletter 19 (1990), pp.9-19. 本誌28-29頁再録。
9 PIAC Newsletter 20 (1991), pp.14-15.
10 これについては山田信夫「日本におけるアルタイ学の現状」PIAC Newsletter 2 (1967), pp.7-9参照。
11 PIAC Newsletter 13 (1982), p.5参照。
12 PIAC Newsletter 26 (1999), p.3参照。残念な誤植で、プロヴォの会議が正しくは第40回なのに、第47回となっている。